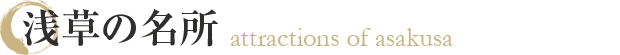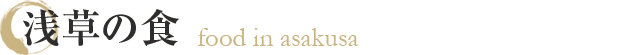お土産に最適な縁起物キーホルダーやストラップを販売しております 有限会社吉田
花やしき

1853年(嘉永6年)に千駄木の植木商、森田六三郎により牡丹と菊細工を主とした植物園「花屋敷」が開園した。当時の敷地面積は約80000m2だった。江戸期は茶人、俳人らの集会の場や大奥の女中らの憩いの場として利用され、ブランコが唯一の遊具だった。
そして1953年(昭和28年)のローラーコースター、1950年(昭和25年)のBeeタワーなど現在あるアトラクションが登場し始めた。長らく入園料を取らず、利用する施設ごとに回数券などで料金を支払う形を取っていた。 2011年(平成23年)3月、旧お化け屋敷跡地に3階建ての新しいビルがオープンした。また、その中にある新お化け屋敷「お化け屋敷 ~桜の怨霊~」も同時にオープンした。
浅草寺

浅草寺(せんそうじ)とは、東京都台東区浅草二丁目にある東京都内最古の寺である。山号は金龍山。本尊は聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)。元は天台宗に属していたが第二次世界大戦後独立し、聖観音宗の総本山となった。観音菩薩を本尊とすることから「浅草観音」あるいは「浅草の観音様」と通称され、広く親しまれている。東京都内では、唯一の坂東三十三箇所観音霊場の札所(13番)である。江戸三十三箇所観音霊場の札所(1番)でもある。
【雷門】
表参道入口の門。切妻造の八脚門で向かって右の間に風神像、左の間に雷神像を安置することから正式には「風雷神門」というが「雷門」の通称で通っている。慶応元年(1865年)に焼失後、長らく仮設の門が建てられていたが昭和35年(1960年)、約1世紀ぶりに鉄筋コンクリート造で再建された。実業家・松下幸之助が浅草観音に祈願して病気平癒した報恩のために寄進したものである。門内には松下電器産業(現パナソニック)寄贈の大提灯がある。三社祭の時と台風到来の時だけ提灯が畳まれる。
浅草 仲見世

雷門から宝蔵門に至る表参道の両側にはみやげ物、菓子などを売る商店が立ち並び、「仲見世」と呼ばれている。
商店は東側に54店、西側に35店を数える。寺院建築風の外観を持つ店舗は、関東大震災による被災後、大正14年(1925年)に鉄筋コンクリート造で再建されたものである。
浅草 新仲見世

浅草の商店街を東西に突き通る新仲見世商店街。通商「しんなか」。全長380Mに及ぶ浅草最大のアーケードで108店舗が並ぶ。 仲見世に対して「新仲見世」とは、江戸の仲見世、昭和の新仲見世といったものである
伝法院通り

仲見世柳通りと浅草六区通りに挟まれた、伝法院を中心に左右約200メートルからなる通りを指す。さまざまな名所や店舗が並んでいるにぎやかな通りで、江戸情緒のある町並みで、下町散策を楽しめる。
浅草すしや通り

浅草すしや通り商店街は、長い浅草の歴史とともにその歴史を重ねてきた全覆型アーケード。
雷門通りから浅草公園六区興行街に通ずる道幅8メートル、延長100メートルの商店街で、浅草1丁目に位置しており、伝法院通り・たぬき横丁・ひさご通り等とともに公園六区興行街にはいる道筋として古くから人通りで賑わっている
六区ブロードウェイ(映画館通り)

伝法院通りからつくばエキスプレス・浅草駅へと通じる、全長約100メートルの通り。
浅草を育て浅草を愛した文人や芸人の名跡を残す商店街である。 通りの両脇の街燈には、浅草を代表する芸能人を紹介する写真と解説が設置されており、入口の両方に石塔が設けられている。江戸の街並みを模する伝法院通りにつらなるため、その雰囲気を損なわないようにする演出している。
それほど長くない通りだが、飲食店が比較的多いのが特徴。
浅草地下商店会

銀座線浅草駅改札口(東武への)を出るとすぐ左が日本初めての地下商店会。 いろいろなお店があり、マスコミにもよく紹介されている。雨のときなど浅草寺方面へぬれずにいける近道になる。噂によると浅草美人がいるところと評判。
ひさご通り

浅草北西部、六区興行街から言問通りまで、全長180Mのアーケード式商店街。
大正13年の区画整理後、沿道商店の自己資金による道路整備をきっかけに誕生した。その翌年、かつてあった浅草公園のひょうたん池に因み「ひさご通り」と名付けられた。
昭和30年に東京都正式許可第一号の鉄筋全覆開閉式アーケードにして以降、浅草らしい「粋」をコンセプトとした「江戸街構想」を実現しようとしている。
かっぱ橋道具街

台東区西浅草 - 松が谷地区にある、食器具・包材・調理器具・食品サンプル・食材・調理衣装などを一括に扱う道具専門の問屋街の事である。
日本一の道具街であり、かっぱ橋、合羽橋道具街、かっぱ橋道具街とも呼ばれる。 河童をマスコットにしているが、「河童橋」ではない。
浅草公会堂

1977年にこけら落とし。毎年1月に新春浅草歌舞伎が開催されるほか、浅草芸能大賞、漫才大会(年忘れ漫才競演公開録画)などが開催されるほか、映画の上映会、舞踊などが主に開催されている。座席数は1082席。ただし、年末年始と1月の大半は新春浅草歌舞伎が開催されるため、一般での利用はできない。